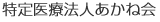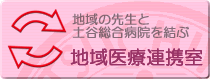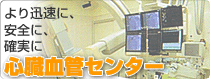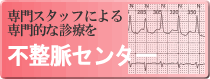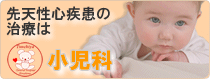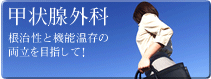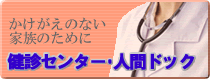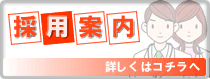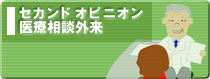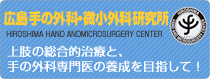日ごと暖かさの増す快い季節となりました。桜の蕾も膨らんで、いよいよ春の訪れが感じられます。
今回のテーマは お酒と健康 についてです。
2014年3月
アルコールの吸収・分解
お酒の主な成分はアルコール(エタノール)と水です。お酒を飲むと、約20%が胃から、その他の大部分が小腸で吸収されます。吸収されたアルコールは血液に溶け込み、全身へと拡散された後、肝臓まで運ばれます。
肝臓ではアルコールの約90%が代謝されます。肝臓のアルコール脱水素酵素により、アルコールはアセトアルデヒドという物質に分解されます。いわゆる「酔った」状態、顔が赤くなったり、動悸や頭痛、吐き気をもよおしたりするのは全てこのアセトアルデヒドが原因なのです。アセトアルデヒドはアセトアルデヒド脱水素酵素によって酢酸に分解され、酢酸は、炭酸ガスと水に分解され、最終的には尿や呼気として体外へ排出されます。
急性アルコール中毒って?
そもそも「酔い」の症状とは、爽快期→ほろ酔い期→酩酊(めいてい)初期→酩酊期→泥酔期→昏睡期、というステップで進んでいきます。酔いの程度に合わせて徐々に脳が麻痺していきます。この酔いの症状は、血中のアルコール濃度をもとに分けられており、濃度と症状が比例しているのです。
通常、血中のアルコール濃度が最高点に達するには、30〜60分ほどの時間がかかります。しかし「イッキ飲み」をすると大量のアルコールが一瞬にして体内に入るため、肝臓での代謝が追い付かず、酔いのステップを跳び越えてしまいます。急激な血中アルコール濃度の上昇により泥酔期、最悪の場合、昏睡期に至ることもあり得ます。
ちなみに「泥酔期」とは立つこともままならない千鳥足、呂律が回らない、話している言葉もメチャクチャな状態。翌日記憶がない…という人は、このステップまで進んでいたといっても良いでしょう。最後の段階「昏睡期」ではその名のとおり昏睡状態、失禁、呼吸の麻痺や死亡に至るような極めて危険な状態を表します。脳の呼吸機能が麻痺し、呼吸停止や心停止によって死に至るのが、急性アルコール中毒による死因です。
イッキ飲みをし、グラスを置いた直後に泥酔期、昏睡期に入るわけではありません。アルコールは徐々に徐々に脳を蝕んでいきます。「まだ大丈夫」「案外平気」こういった油断のもと、イッキ飲みの後もお酒を飲み続けていると……もう、分かりますね。
こんな危険をはらんだイッキ飲み。場の勢いだからといって、絶対にやってはいけません!!
二日酔いの原因や症状・治し方
二日酔いとは、お酒を飲んで時間が経っても不調が続く状態です。ここでは原因とそれぞれの症状について説明します。
- アセトアルデヒド:上記の通り肝臓で生成される物質です。これが解毒されずに蓄積されて起こるのは頭痛、ダルさ、吐き気、疲労です
- 脱水:二日酔いで最も多いのが脱水を原因とする頭痛、身体疲労、吐き気、食欲不振などの各種症状です。アルコールには利尿作用があるため、飲酒により摂取した水分以上の水分が失われます。アルコール50gで600〜1000ml(ビール500mlを2本飲むと、1L近く)の水分が失われる計算となります。ビールよりもアルコール度数の高いお酒なら、飲めば飲むだけ脱水のリスクが上がります
- 低血糖:飲酒によるアルコールは全て肝臓で処理されます。アルコールを分解している間、肝臓はそちらを優先させ、他の働きを休ませてしまいます。中でも二日酔いの原因となるのが、糖(グリコーゲン)の生産不足です。通常、肝臓は糖分を貯蔵し、必要に応じて供給しているのですが、このストックは多くて8時間分程度です。アルコールの分解に肝臓が使われることにより、糖分が不足してしまうのです。脳の働きに糖分が必要であることは有名ですね。糖の不足により、頭痛、眩暈、筋肉痛などが生じます
- 胃酸過多:アルコールは胃酸の分泌を促します。過剰な胃酸により、胃のムカムカ、吐き気や食欲不振、下痢を伴った症状が現れます
二日酔いになってしまったら
アセトアルデヒドを解毒し、不足している水分を補いましょう。
スポーツドリンクは代表的な二日酔いの薬です。排尿により失われたナトリウム、カリウムなどの電解質を補給し、人体に近い浸透圧であるため吸収が早いのが特徴です。お味噌汁も水分、栄養補給に優れています。アセトアルデヒドの解毒にはしじみやゴマ、ひまわりの種などが優れています。アルコールの分解を早めるため、しじみや魚介類入りのお味噌汁なんかも良いかもしれません。素早い水分補給により二日酔いを治したい場合は市販のドリンクなどが有効です。
吐き気がひどい時には吐き気止めや胃薬を。
低血糖による二日酔いの場合、すばやく糖分を摂らなければなりません。
中でも果糖を含んだフルーツジュースは有効です。このとき、酸性のりんごジュースではなく、オレンジジュースやレモンの搾り汁、食品ではコーンフレークなども効果的です。「迎え酒」はお酒の麻酔で二日酔いを悪化させるだけなので避けましょう。
恐ろしいアルコール依存症
習慣的にお酒を飲んでいると、もっともっとと気持ちよく飲みたくなり、アルコールの摂取量が増えていきます。初めは1合の日本酒でほろ酔い気分を味わえていたのに、3合でも物足りなくなってくる。これを 耐性 といいます。そしてアルコールには依存性があります。耐性のついた体でアルコールを摂取し続けると、程良い量で止めることが出来なくなります(コントロール障害)。一旦コントロール障害を起こしてしまうと、一生もとには戻りません。断酒を貫き通すしかないのです。
主な症状としては手の震え、発汗、不眠、焦燥感。鬱っぽくなったり怒りっぽくなったりする人間性の変化は、周りとの人間関係にも大いに影響します。家庭が壊れ、職を失い、健康な人間生活を全うすることさえ出来なくなってしまうのです。
お酒の適量、正しい飲み方
「適量」といっても、その量は人によってさまざまです。アルコールの許容量は性別、年齢、体の大きさ、その時の健康状態など、色々な要素が関係するためです。日本人には「お酒に弱い体質」の人が44%存在します。つまり、約2人に1人はお酒に弱いと言えます。
日本では、1日の適量は日本酒で1〜2合と言われています。ただしこれは、男性で、かつ「お酒に強い」タイプの場合です。日本酒1合のアルコール量は、ビール大瓶1本、ウイスキーW1杯、焼酎半々のお湯割りコップ1杯、ワインはグラス2杯に相当します。女性の適量は男性の約半分と言われていますが、これは体格差の他、女性ホルモンの影響によるものと考えられます。女性ホルモンはアルコールの分解作用を抑制するとされます。また、一般に高齢になるほどアルコールの代謝能力が低下します。この低下に気付かないまま若い頃と同じ量のお酒を飲むと、適量ではなく過量です。
「適量のお酒は体にいい」と言われますが、かといって毎日の飲酒は肝臓にダメージを与えてしまいます。体のため、1週間に2日以上の休肝日を設けましょう。
お酒と薬の関係
「薬と一緒にお酒を飲んではダメ」とよく言われますが、薬を飲んだからといって、夕食時のビールをやめられない人は多いでしょう。薬の種類やお酒の量によって影響の少ないものもありますが、中には非常に危険なこともあります。風邪気味なのに大事な接待があるからと、風邪薬を飲んでから酒席に臨んだりしてはいけません。帰りに電車のホームで意識を失ったら、命に関わるかもしれません。どんな薬がお酒と一緒に飲むと危険なのか、基本的なことを知っておきましょう。
そもそも薬とアルコールはどちらも肝臓で代謝されます。肝臓がアルコールの解毒に忙しくなると薬が遅れて効きすぎるし、その逆もあり得ます。お酒と一緒に飲むと危険な薬の例が以下のとおりです。あなたの飲んでいる薬に当てはまるものはありますか?
- 抗ヒスタミン薬
風邪薬、抗アレルギー薬に含まれる抗ヒスタミン薬には、眠くなるものが多いです。お酒の効果と合わさって眠気が強く現れることがあります - 咳止め薬
咳の反射神経を抑制する薬は眠くなることがあるため、抗ヒスタミン薬同様に眠気が生じます - 睡眠薬
アルコールと同様に脳の神経の興奮を抑えるため、効きすぎることがあります。中でもバルビツール系の睡眠薬はアルコールと同じく肝臓で分解されるので、結果的に両者の分解が遅くなり大変危険です - 精神安定剤
アルコールと同様に脳の神経の興奮を抑えるため、効きすぎると昏睡、意識を失ってしまう危険があります - 降圧剤
アルコールには血管を拡張し、血圧を下げる働きがあります。血圧降下剤とあわせると血圧が下がりすぎ、脳貧血で立ちくらみなどを起こすことがあります - 糖尿病治療薬
糖の分解を促進して低血糖を起こすもの、分解されずに体に溜まってしまったアルコールのせいで「酔い」の症状が強く出るものなどがあります - 解熱鎮痛剤
アスピリンなど解熱鎮痛剤は、一般的に胃にダメージを与えがちです。同様に胃のムカムカを引き起こすアルコールとの相性は良くありません。また、アセトアミノフェンという解熱鎮痛剤は、お酒と一緒に飲むと肝臓を傷付けてしまうことがあります
お花見シーズンです。体を労わり、正しい飲み方でお酒と付き合いましょう!