
| 透析日 | 月水金 | 午前 | 9:30~ |
|---|---|---|---|
| 午後 |
15:30~ 16:00~ 17:00~ 18:00~ |
||
| 火木土 | 午前 |
9:00~ 9:30~ |
|
| 午後 |
14:00~ 14:30~ 17:00~ 18:30~ |
||
| 透析療法 |
血液透析療法(HD) 血液透析濾過(O-HDF) 間歇補充型血液透析濾過(I-HDF) 在宅血液透析導入指導(HHD) |
 |
|
| 透析台数 | 160台(全床テレビ完備) | ||
| 設備環境 | 全床にテレビ、電動チェアーまたは電動ベッド完備 | ||
| 旅行透析 | 受入可能→下記連絡先まで | ||
| 透析スタッフ | 医師3名 / 看護師41名 / 臨床工学技士49名 / 事務8名 / 放射線技師1名 / 管理栄養士2名 / 理学療法士1名 | ||
| 連絡先 | 電話:082-542-7271 / FAX:082-542-7278(担当:広本) | ||
当クリニックは広島市中心部、平和記念公園正面の土谷総合病院裏に位置している外来血液透析患者様専用の透析センターです。
最新の全自動透析装置を配備し、160名の患者様が同時に血液透析を行なうことが可能となっております。現在、約450名の患者様が透析治療のために通院されておられます(2018年現在)。
この全自動透析装置を使用するためには、透析液の清浄化が必須です。当クリニックでは開院当初(2001年7月)から透析液の清浄化に力を注いでおり、透析用の水は常にクリーンな状態に保っています。このきれいな水を全ての患者様に使用することで、合併症低減を図っています。
また高度で安全な医療を提供できるように、院内の委員会活動も活発に行っており、いかに患者様へ貢献できるかを日々考え努力しています。地域の中核となり得る透析センターを目指しています。
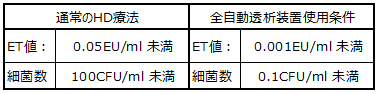
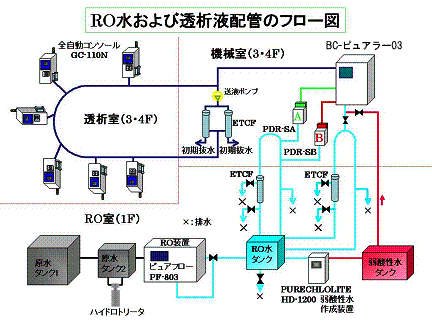
多段式のループ配管を設置する事により、RO水・透析液の停滞をなくし、菌の繁殖を防止しています。また、1次~3次までのETRF(エンドトキシン捕捉フィルター)を設け、さらに徹底したET除去を行っています。
1.個人栄養指導
患者様及びそのご家族様を対象に、管理栄養士による個別の栄養指導を実施しています。
今までの検査データを把握した上で患者様やご家族様から食習慣や食事摂取状態などの情報を収集し、個人個人の食生活に合った食事ができるよう手助けをしています。
これからの食生活を重荷に感じない様な、問題を解決するためのアドバイスを心掛けて指導をしています。
2.腎臓病教室
主に季節に関するテーマを決めて、月2回栄養のことだけでなく料理について、その他全般についてお話をしています。
どなたでもご自由にご参加することができ、質問、相談も受け付けています。
|学術委員会|バスキュラーアクセス管理委員会|リスクマネジメント委員会|フットケア委員会|感染対策委員会|水質管理委員会|患者教育委員会|スタッフ教育委員会|災害対策委員会|業務改善委員会|衛生管理委員会|在宅血液透析(HHD)委員会|他|
当クリニックでは最新の医療を学び、患者様に提供できるよう学会、研究会への参加や研究発表を積極的に行なっております。
主な参加学会
日本透析医学会 / 日本血液浄化技術学会 / 日本医工学治療学会 / 日本人工臓器学会 / 日本臨床工学会 / 日本腎不全看護学会 / 中四国臨床工学会 など
主な参加研究会
日本アクセス研究会 / 在宅血液透析研究会 / 中国腎不全研究会 / 日本HDF研究会 / I-HDF研究会 / ハイパフォーマンスメンブレン研究会 / 高齢者腎不全研究会 / 腎栄養代謝研究会 / VA超音波研究会 など
当院では患者様の生命線である「シャント」を適正に管理するために、穿刺教育、シャントトラブル予防、定期的なエコー評価などを実施しています。また透析室でのエコー評価を行うことで確実な穿刺とシャント機能の評価が常に可能となりました。
一人一人が業務上の間違いを回避するように努める事が、医療事故防止につながります。しかし、現在のように高度化・複雑化した医療を提供しなければならない状況下においては、いかに注意を喚起しても事故は発生します。そこで、インシデント・アクシデントに関する情報を収集分析し、医療従事者にフィードバックする事で、医療事故の起こりにくいシステムを検討する事が、医療事故防止に繋がると考えます。
患者様、医療従事者を傷害から保護し最善の医療・看護を提供します。
一般的に糖尿病があると、細菌感染の危険性が高くなります。また動脈硬化が進行すると、足の血流の低下や末梢神経障害により、知覚が鈍くなると足病変に気付くのが遅れる傾向にあります。
当クリニックではフットケア委員の指導のもと各受け持ちスタッフが足の観察を定期的に行い、下肢の切断に移行しない様に努力しています。
平成19年度よりSPP(皮膚灌流圧検査)を導入し、足病変の予防的ケアと早期発見・治療に尽力しており、患者様自身が足の手入れをできるように、セルフケアの指導も行っています。
*1:SPP(Skin Perfusion Pressure:皮膚灌流圧)検査は、非浸襲的に末梢循環血流量を測定することができ、血管の石灰化や浮腫・貧血などの影響を受けにくいため、末梢微小循環評価に有用とされています。
透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(四訂版)に基づき、感染対策予防、教育、研修を行い、集団院内感染(アウトブレイク)を防ぎ、患者と医療従事者の安全を確保する事を目的にしています。
血液透析を始められた患者様やご家族様を対象に、より快適な透析ライフを送れるように、経験豊富なスタッフが異常の早期発見や自己管理について勉強会を行なっています。
全国の在宅血液透析患者様は約650名程度(2017年末)とまだまだ少ないですが、在宅血液透析を行なっている方々は、通院回数の大幅な減少、家族との時間の増加、自由な治療計画などが実現できています。
当院では土谷総合病院と連携し在宅血液透析移行に向けたお手伝い(教育)を行なっており、現在(2019年4月)までに19名の患者様が在宅血液透析に移行されました。